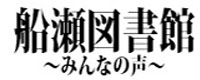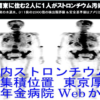日本の林業の未来を変えた木材低温乾燥装置「愛工房」。
日本の大規模木造建築に革命をもたらした「KES構法」。
この2つが組み合わさり、地震に負けない、安全な空気で満ちる、〝呼吸住宅″が出現した!
新築住宅を考えている人や、今のありように工夫したい工務店の人には必読の本です!
はじめに
この本を企画した当初から、題名は「木造都市の夜明け』と決めていました。題名にこだわったのはある人との出会いと、人と人との結びつきからでした。
2004年の夏に木材乾燥装置を開発した数力月後、その人は、現れました。業界誌「ウッドミック」の編集長(当時)、高島太加夫氏です。
終生の盟友となりました。
2005年の初めには、開発して間もない乾燥装置を同誌で紹介していただきました。
さらに、8月号では乾燥装置の第1号を設置した東京都森林組合奥多摩加工所について、関連記事と合わせて18ペ—ジにわたって記事が掲載されました。
その後も、当社のこと、「愛工房」のこと、私のことを頻繁に紹介していただきました。メーカー、業界から相当の抗議、圧力があったことも聞いています。
当初、高島氏には、「当社は広告は一切出しません。それでよければよろしくお願いします」と申し入れていました。
出会ったとき、高島氏72歳、私は63歳でした。
2O11年6月、高島氏が78歳で第一線を退く際、これまでに名刺交換した人だけでも数千人、その中のひとりを取りあげて書くと言われました。
それが「愛工房」のことであり、伊藤好則のことだと言われたとき、驚きと恐縮の極みでした。その原稿は間もなくして届きました。
「ウッドミック」2007年9月号では、「本誌は提唱する、そのテーマが『木造都市の夜明け』なのは何故か」を表題として、「木造都市」構想は日本人初の特異な思い入れによって誕生したーーと書かれています。
そこには、環境ジャーナリストの船瀬俊介氏と私の写真、別のページには本書の主人公でもある(株)シェルター社長の木村一義氏の写真が載っていました。
この3人は一冊の本が私たちを結び付けてくれました。
それは、船瀬俊介氏の取材活動などを手伝っていた際に出版された氏の著書『コンクリ—卜住宅は9 年早死にする』です。
これにより、木村一義氏に出会いました。
高島氏と木村氏は旧知の間柄でしたので、これで柱が4本になり、日本の木の、木造建築の復権運動「木造革命」が始まりました。
みなさんは「木造都市」にどんなイメージを持つでしょうか。
建物に使う素材はすべて、かつてより自然からいただいていました。土や石を活かして建物に使った地方においても、木があるところの建物は木を使っていました。
特に日本の建物は昔から木造でした。日本の気候風土に合わせて、昔から積み上げてきた知識や技術を集積した建物が現在も多く残っています。
江戸の家並みや建物は諸外国にひけをとらない、それどころか世界から羨望の目で見られていた「木造都市」でした。
江戸時代にはすでに、日本各地に「木造都市」が存在していました。樹木たちの年輪からみればほんの少し、150年ほど前の話です。
それが、建物も文明開化の音頭に引きずられて、日本の呼吸する建物の良さを誇リにすることよリ欧米からの工業製品を求め、国産でも生産し供給するようになりました。
ついには使用する建材のほとんどを呼吸しない建材で建てた住まいとなってしまいました。これが命・健康に良いわけがありません。
戦後、住まいのほとんどを気侯風土に反した鉄筋コンクリート造にした沖縄。
熱を溜めた建材に囲まれた部屋の中では、夜の暑さは格別だと思います。建物が呼吸しないで人だけが呼吸するのですから。
2016年9月のことですが、テレビのドキュメンタリー番組の中で、全国の砂利組合のアンケートによる驚くべき数字を見ました。

コンクリートに使う良質の砂利、砂の85%が不足していると。すると、コンクリートを使った建物の85%はどんな砂利や砂が使われるのでしょうか。
また、現在建てている建物だけでなく、これから建てる建物にはもっと不足してくるのでしょう。
砂利や砂は、生産できません。それに比べて樹木は生産可能です。
「4階建て木造ビル」の説明で、当ビルが、鉄筋コンクリート造だったらと試算し、比較した内容も添付しています。興味ある結果が出ました(204頁) 。
どれだけの砂利、砂を必要とするのか、余分に何台のダンプカーやミキサー車が道路を傷めて走るのか。
木造と鉄筋コンクリート造では、環境負荷がまったく真逆の結果です。命を大切にする国、命を活かす国であって欲しいと思います。
私の言う命とは、人の命、地球の命です。それを守ってくれるのが樹木たちの命です。
(株)シェルターの木村社長から、2年ほど前に、聞き慣れない「ウッドファースト」という言葉を耳にしました。
木でできるものは木を使う。

木でできないところを鉄やコンクリートを使う。これが「ウッドファースト」の思想です。ヨーロッパではすでにこの方向に進んでいると聞きました。
森林王国・日本で、これからもっとも必要なのは「ウッドファースト」の考え方と実践ではないでしょうか。
なによりも子どもたちに命を残せるのですから。
本書をお読みいただき、みなさんとともに「木造都市の夜明け」を迎えることができれば、著者としてこれ以上の喜びはありません。
| 木造都市の夜明け |
||||
|