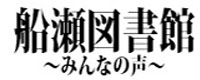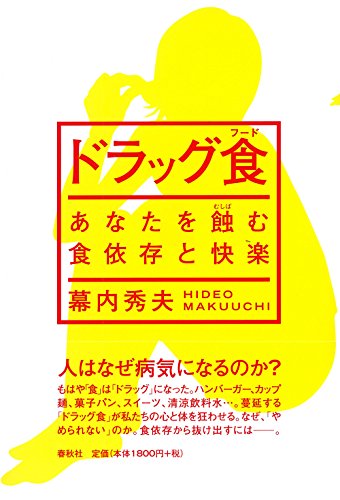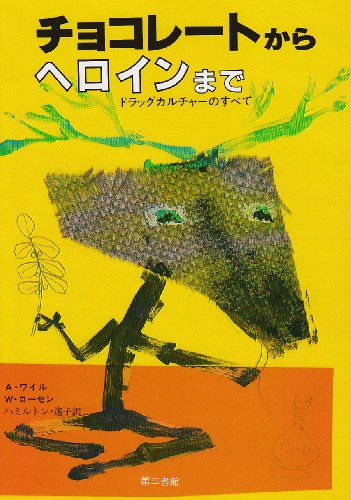人はなぜ病気になるのか?もはや「食」は「ドラッグ」になった。
ハンバーガー、カップ麺、菓子パン、スイーツ、清涼飲料水…。
蔓延する「ドラッグ食」が私たちの心と体を狂わせる。
毒や薬は生まれながらにして毒や薬なのではなく、あくまでも、人間によって毒にも薬にもなるのである。
(船山信次著『毒と薬の世界史』中公新書)
食物への依存という、つかみどころのないコンセプトは、正常な行動と人生を狂わせてしまう本格的な依存症のあいだに広がりつつあるグレーゾーンに私たちを向きあわせる。
(デイミアン・トンプソン著『依存症ビジネス』ダイヤモンド社)
「食」のドラッグ化が始まっている
本人は「おいしいから食べたくなる」と考えているようだが、「無性に食べたくなる」、「食べないとイライラする」という状態は、アルコールやタバコ(ニコチン)、あるいはコーヒー(カフェイン)などの依存症に、限りなく近い。
アルコールやタバコ、コーヒーの場合も、それらを口にできなければイライラし、口にすれば精神的に落ちつくことができる。
そのため、やめようとしても容易にやめられずに苦労することになる。
それらと変わらないことが「普通の食事」に起こっているのである。これは決して大げさな話ではない。
日本ではまだこのような例が問題視されることは多くないが、肥満大国アメリカを見てみれば決して大げさではないことがわかる。

詳細は本文で詳しく触れるが、ジャンクフードの登場が肥満を増やしたことに異論を唱える人はいないだろう。
肥満大国でもわかっていることである。
だが、アメリカでは毎年二〇万人もの人が、肥満や糖尿病が原因で消化器官(胃や小腸など)の切除手術を受けている。
手術を選択する理由はそれぞれだと思うが、急激な減量が必要な超肥満の人たちがほとんどだ。
この手術を受けるためには大変な費用がかかる。わずかだが死亡する例もある。
後遺症で苦しむ人も少なくない。
長期的な安全性については、まだまだわからないことが多い。それでも、手術を選択するのは、食事や運動で減量することが難しいからである。
あるレベルを越えて太ってしまうと減量することが難しくなるということもある。

ジャンクフードばかり食べていたらどうにもならないとはわかっていても、やめられないのである。
ジャンクフード「依存症」と呼んでもいいだろう。
「おいしい」から「快楽」へ
私は医療機関でたくさんの患者さんの食生活を見てきたが、アルコール、タバコ、カフェイン、スイーツのどれも「ない」人はきわめて少ない。
どれもないのは、おそらく三〇〇人に一人くらいだろう。
大酒飲みで、ヘビースモーカーの人は、甘い菓子類を食べることは少ないが、そのような人が仮に入院すると、晩酌はできないし、タバコも喫いにくくなる。

そうなると、甘い菓子類に手を出すことが多い。
最近、企業には「置き菓子」が置いてあるところが増えている。
子どものころ、多くの家に「置き薬」が置いてあった。
「越中富山の置き薬」と呼んでいたが、業者が定期的にまわってきてなくなった薬を補充していた。
どうやら、置き菓子はそれと同じようなシステムになっているらしい。
なぜ、そのようなものが登場するようになったのか。
ひとつには、夜型生活になり、昼食から夕飯までの時間が長くなり、一時の小腹を満たす必要が生じていることがある。
もうひとつは、タバコを喫いながら仕事をすることが難しくなっていることがあげられる。
コンビニエンスストアにも、男性用スイーツコーナーが増えている。これも禁煙運動の影響だろう。
きちんと「分煙」せずに「全面禁煙」を実施した企業は、肥満や糖尿病が増えてしまう可能性が高い。
『チョコレートからヘロインまで』(第三書館)の著者、アリゾナ医科大学のアンドルー・ワイルは次のように書いている。
何に対するものにせよ、依存状態を解くのはやさしいことではない。たいていの場合、ただある依存を別のものへの依存に代えるだけにすぎず、それでより多くの自由を獲得できるわけではない。
二〇〇五年の『食育基本法』制定以来、多くの自治体が「食育」に熱心に取り組むようになった。
それはそれでいいことだと思うが、そのほとんどが「野菜を食べましょう」、「朝ごはんを食べましょう」、「バランスの取れた食生活をしましょう」などと「食べる」ことばかりを推奨する。
行政は、「○○を食べるのをやめましょう」、「○○を減らしましょう」という提案をしない。
○○に当てはまる業界からの反発を恐れているのだろう。
そのため、対策とは名ばかりで、税金を使ってただお茶を濁しているだけになっている例が多い。
いま大切なことは、何を食べるかではなく、何を食べないかをきちんと提案することである。
「食のドラッグ化」を甘く見てはいけない。
そして、日本はその対策をとることが決して難しくない。まだ間に合うのである。
そのことを多くの人たちに知っていただきたい。その思いで本書を執筆させていただいた。
| ドラッグ食: あなたを蝕む食依存と快楽 |
||||
|