紺色の空高く、銀色に小さく光る点……。それが、急速に大きくなる。
銀漢の奇怪な機体。飛行音はほとんど聞こえない。一気に降下してミサイルを連射。
炎の黄色い弾道を残して、地上の群衆近くで爆発。爆煙が上がる。
人々は、叫び声をあげて逃げ惑う。血まみれで倒れる。砂煙と悲鳴。街路は一時、騒然となる。そして、静寂ーー。
銀色の細長い異様な機体は、何ごともなかったかのように、ゆっくり高度を上げ、天の果てに消えていく。
地上には、おびただしい数の死体。人々の呻き声。煙をあげて燻る民家。
そこはただ、不気味な静けさが支配している。
これは、SF映画の一場面ではない。
いまも、地球上のどこかで実際に起きている血の惨劇である。高空から飛来し、地上の人々を襲ったのは無人攻撃機「プレデター」だ。別名、“戦慄の暗殺ドローン”……。
ドローンとは、無人飛行機をはじめとした「無人兵器」の総称だ。
われわれには、戦争といえば歩兵が銃を撃ち合い、空には戦闘機が舞う、というイメージがある。しかし、昨今の戦争は、まったく様変わりしている。

この無人攻撃機は、「プレデター」一九九五年ごろより中東や東欧の戦闘地域に実戦配備されている。
「プレデター」(Predator)とは“捕食動物”という意味だ。
まさに、獲物を狙う猛禽のごとく、高空から音もなく忍び寄り、襲いかかってくる。無人機にもかかわらず、高性能の攻撃能力を装備している。
機首部分が異様にふくらんでいる。そこには、可視光・赤外線カメラ、レーザー照準機などが搭載されている。
胴体後方にあるプロペラの回転を絞れば、ほとんど無音で“獲物”に忍び寄ることもできる。
操縦席はどこにあるのか?
“捕食動物”は、超遠距離からの遠隔操作が可能だ。地球の裏側にいても操縦できる。
結論をいえば、操縦席は米国にある。具体的には、CIA本部のオペレーション・ルームが“操縦室”となる。
“パイロット”は、巨大モニターに映し出される映像を見ながら操縦する。
そして、地上の“テロリスト”を目視すると、搭載ミサイルの照準を合わせて攻撃する。
モニター画面に爆煙が上がり、何人もの身体が粉々に吹き飛ぶ。これで、任務完了。ビルの外に出ればそこは大都会の雑踏だ。
カフェで友人とハンバーガーを食べて談笑したあと、地下鉄で帰宅。「パパ、お帰り!
」と小さな息子が抱っこをせがむ。
抱き締めて頬ずりする。
息子がかわいい声で聞く。
「お仕事どうだった?」
「うん、順調さ・・・」
「フーン、やったね!」
罪なき民間人を一瞬で爆殺
いまや米国が関与している戦地では、ニ四時間、昼夜を分かたずドローンが空中高く待機している。
そして“不審な”者を発見すると、カメラで捕捉してミサイル攻撃する。
モニター画面で目視したターゲットがテロリストだという保証はどこにもない。それでも怪しいと思えば、ミサイル発射ボタンを押す。
当然、民間人への誤爆は避けられない。

悲劇は続発している。国連の調査によれば、二00四年以降、パキスタンだけで少なくとも四00人以上の民間人が、無人機ドローンの攻撃で虐殺されている。
「母は、子どもたちと畑に出て野菜を収穫していました。その時突然アメリカの無人機が攻撃してきて母の体は吹き飛びました」(「クローズアップ現代」二0一三年九月二六日放送)
二0―二年、米軍のドローンによる“誤爆”で母親を失った、パキスタンのラフィーク・ウル・レフマンさんは怒りの証言をする。
「女性や子どもがテロに関わっているわけがないじゃないか。アメリカのやっていることは、ただの冷酷な殺人行為です。こんなひどいこと、許せません」(同番組)
これら無人機の“誤爆”による民間人の大量虐殺こそ、米国による国家テロそのものだ。無実の肉親を惨殺された家族が絶望とともに復讐の自爆テロに走ってもなんら不思議はない。
つまり、ドローン・ウォーズがテロを拡大再生産しているのだ。米国は、殺される側の感情をまったく無視して“テロとの戦争”の大義を掲げる。
傲慢、欺瞞、かつ滑稽というほかない。
「パキスタン人とイエメン人は、無人機攻撃は、国家主権の侵害だとして反発した。目に見えない飛行機からいつ何時ミサイルが飛んできて殺されないとも限らない、という思いが、明らかにパキスタンとイエメンの人々を不安に陥れていた。
無人機攻撃に対する怒りこそ、テロリストを増殖させる元凶だと、主張する人もいた」(リチャード・ウィッテル『無人暗殺機ドローンの誕生』文藝春秋)
しかしバラク・オバマ大統領(当時)は、二0一六年五月、ドローンの使用条件の厳格化を確約しながらも、“対テロ戦争”におけるドローンの必要性を支持する姿勢を崩していない。
映画『ターミネーター』が現実になる?
本書『ドローン・ウォーズ』の副題に注目してほしい。
ーーー“やつら”は静かにやってくる。
ここでいう“やつら”とは、「プレデター」だけではない。たとえば、“鳥型ドローン”や、なんと“蚊型ドローン”まで開発されている。
前者は、見た目はハチドリそっくり。空をはばたきながら、ターゲットの動向を監視する。
後者は、まさに蚊と同じ大きさで、室内に侵入しても誰も気づかない。部屋のすみで超小型カメラで監視することも可能だ。
それどころか、ターゲットの皮膚に止まって血液やDNAを採取することも可能になるという。
あるいは、ロボット犬「アルファ・ドッグ」という“軍用犬”も開発されている。その動きを映像で見ると、本物の犬そっくりだ。
それがさらに巨大化したものが、“ロボット軍馬”だ。
荒れ地などで武器や食糧を輸送するのに役立つという。犬や馬で驚いてはいけない。二0一三年、巨大IT企業グーグルが、ロボット産業に参入したことが報じられた。
そこで開発されているのが、“ロボット・ソルジャー”だ。
まだ「開発段階」と断っているが、走る姿など、その動きは人間とまったく同じ。
軍服を着せて、ヘルメットをかぶせたら、人間の兵士と見分けがつかない。このロボット・ソルジャーに、人工知能(AI)が搭載される。
いまや人工知能は、チェスや将棋、囲碁の世界チャンピオンを破るほどに進化している。
おそらくロボット・ソルジャーは、みずから“敵”を判断し、ターゲットを即座に射殺するようになるだろう。
そしてその頭脳は、みずから学習し、進化していく。専門家は「人工知能が自我を持つのも時間の問題」という。
ここまで読んで、傑作SF映画『2001年宇宙の旅』(一九六八年)を想起する方も多いだろう。
木星探査宇宙船のコンピュータが人間に反乱を起こし、宇宙飛行士を殺害するストーリーだ。
あるいは映画『ターミネーター』(一九八四年)を想起した方もいるだろう。やはり、人類に対する機械の反乱がモチーフだ。
米国防総省(ペンタゴン)は、真剣に人工知能と人間との戦争勃発を恐れている。
ペンタゴン高官のポール・J・セルヴァ大将が、はっきりこう述べているのだ。
「ペンタゴンは、そのような疑問(“ターミネーター”の攻撃がありうるかどうか)に答えるために調査をしている」
あらゆる戦争は仕組まれている
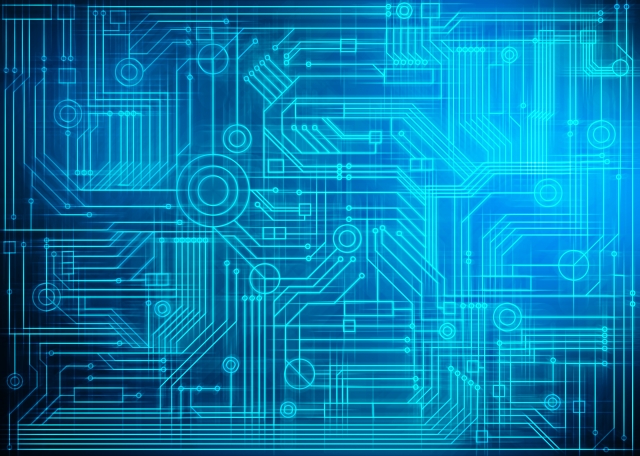
軍事開発の進展と脅威は、それだけではない。
人間の精神を支配する「心理兵器」の開発・研究もひそかに進められている。
それは、洗脳、扇動、暴動などを自在に引き起こすことができる。人類の精神を自在に操れるということは、人類を完全奴隷化できるということだ。
まさに“見えざる”人類支配兵器なのだ。
同様に“宣戦布告なき戦争”もひそかに進行している。
つまり、究極兵器「HAARP」(高周波活性オーロラ調査プログラム)などによる無差別攻
撃だ。
人工地震、気象災害などを起こし、大量破壊と殺裁を行なう。
さらに、空から毒物、ウィルスなどを撒く“有毒飛行機雲”ケムトレイル。そのほか、人工ウィルスやワクチンを偽装した生物兵器が、いまもわれわれに忍び寄っている。
これら無差別攻撃について、マスメディアは一切触れない。いや、触れることができない。
理由は、地球を支配する“闇の支配者”たちが、それを許さないからだ。
その正体をここで明らかにする。
秘密結社フリーメイソンを母体とする秘密組織、イルミナティだ。
さらにたどれば、“一三支族”と呼ばれる支配層に帰着する。中でも二大勢力として権勢を振るってきたのが、ロスチャイルド、ロックフェラーの二大財閥である。
“かれら”は、「地球人口を七0億人から一0億人に削減する」と公言している。
人口削減のために、“宣戦布告なき戦争”が今日も仕掛けられているのだ。
(中略)
“闇の支配者”たちは、人類のことを「ピープル」ならぬ「シープル」と呼んでいる。それは、羊のように従順で愚かな“家畜”という意味だ。
あなたはまず、その屈辱に目覚めるべきだ。
そして、覚醒した一個の人間として思考し、行動し、生き抜いてほしい。そのためには、まず“敵”を知ることだ。
本書ではその“敵”であるドローン軍団の実態をできうるかぎり精査した。“ターミネーター”の反乱を許さぬためにも、市民の徹底した監視と管理が必要だ。
とくに、未来を担う若い人たちに、本書の一読をすすめたい。
| ドローン・ウォーズ |
||||
|









