札幌の自然食品店「まほろば」主人 宮下周平 連載コラム

Slow and steady……
中学校一年生に上がった時、NHKラジオ講座「基礎英語」を聞き始めた。
初めに、講師の芹澤栄先生から座右の銘「Slow and steady wins the race」との英文を覚えさせられた。
この「遅くとも着実なものが勝利する」の習得のコツ。
残念ながら、ものにはならなかったものの、未だにこの一文だけは、時々口を突いて出る。
この格言ともいうべき「急がば回れ」の教訓は、学習法であり、処世術であり、古今東西の賢人の知恵なのだろう。
しかし、このレースに勝つとは、一体何だろう。
何に勝ったのか、何に勝てば良かったのか、人生終焉を迎えて、自問している自分が居る。
敗戦の焼け野原から、「産めよ、増やせよ」と陸続と生まれた団塊世代前後の我々。
オリンピック景気に煽られ、『列島改造論』に沸き、「大きいことは、いいことだ!」、CMの掛け声に刷り込まれ、国民総動員で、所得倍増の道に駆け上った。
とにかく、「スピード、スピード!ビッグ、ビッグ!!」の連呼は日本中に席巻して渦巻いた。
この高度経済成長は、わが青春の真っ只中で繰り広げられ、大量生産、大量消費の大号令の許、使い捨て文化の花盛りは已む時を知らず、GNP(国民総生産)は世界第2位まで上り詰め、その大躍進は世界の脅威となった。
大母思想
そんな中、どういう訳か、18歳で私は人生をドロップアウトしてしまった。
今思えば、そのような風潮の中、どうしても歯車が噛み合わない大きな何かが、自分を突き動かした。
それは、人生の脱落か、脱出かの岐路でもあったはずだ。
その後、煎じ詰めれば、この大自然界の命は一つという『大母思想』というべき道に出会って15年に及んだ。
この霊性の母性主義の追及が、今のまほろばの根幹を作ったように思われる。
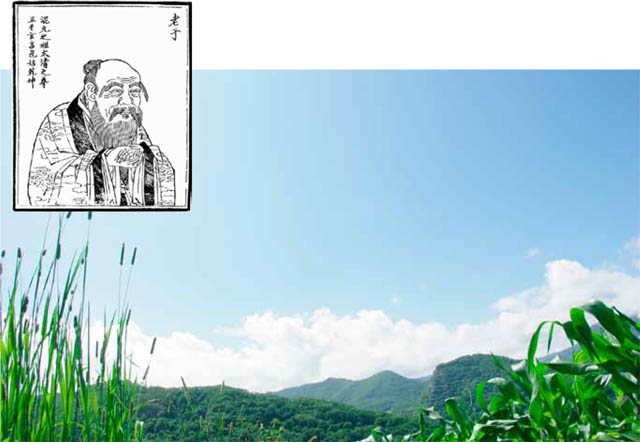
そこに、老子の道があった。「小国寡民」「柔弱之徳」など、小さき事、少なき事、柔らかき事、弱き事、およそ社会の良きとする規範に逆行する概念が、真理としてあったのだ。
老子『道徳経』の一貫していることは「自然の大母に抱かるるを道という」一言だ。
生きとし生けるものたち、万物を生み育てる命の根源を母と言い、「道」という。
中学生で母を亡くした自分にとって、この思想は「なんて、素晴らしいのだろう!」と心に染みたのだ。
この大自然を母と観る。何故か、スーとに入るというか、ピタッと心に嵌った。実に、分かり易いことを、2000年も前に老子は説いていたことに若き心はときめき、感動したのだ。
仏教の如来も、儒教の天も、基教の神も、ギリシア哲学の一者も、謂わんとする処は同じなのだろう。
男社会の末路
あの『三国志』を読めば了解るではないか。戦乱に継ぐ戦乱。覇権を競って殺し合う敵味方。この男達の醜い戦いに、女子供は翻弄され、犠牲になっていた。
この春秋戦国時代。荒れ狂う諸国を回って、「周公の世」に帰るべきを説いた孔子。そんな若き孔子を観て、老子は「無駄骨だ。国は幻想に過ぎぬ。何もせぬことに勝るものはない」と告げた。
長き戦闘に荒れ果てた田畑、堆く積まれた屍を見て、人の、殊に男の権力欲、所有欲のしさ、バカバカしさに、老子は諦念するのだ。
より強大な国を求めて戦う原動力、その象徴するキーワードが、大きい事、多い事、強い事、堅い事……諸々のパワー・ワード、男言葉だ。
しかし、老子は、そんなものは、すぐに費える、消えることを、嫌というほど見て来たのだ。確かに有史は戦争の歴史で、一切が夢のまた夢、邯鄲の夢。
妄想であり、迷いなのだ。
老子の表現は難しく映るが、だが観念の言葉ではない。実体験の生身の活言だったのだ。
母なる真実
そんな壮絶なる地獄絵図の中でも、最後まで諦めずに我が子のことを守り抱きしめている母の姿こそ、「真実だ!」と老子は心底思ったのだ。

そこに人生の真の答えを見出したのだ。その母の愛こそ、天地の愛でもあると知ったのだった。
そして、それを「道」と名付けた。「道」である。この道こそ、古今に通じて古びない、東西に通じて異ならない道標だった。
大きくなろうとする野望こそ、諸悪の根源である、と看破する。
そして、より小さくなることこそ、平安の原理なのだ、と説き始めた。他と衝突も、嫉妬も、嫌悪も起こさない小さき存在こそ、命長らえる叡智なのだ、と。
強き松は、大雪に折れる。しかし柔らかき柳は、しなやかに雪を躱す。強き野獣は疎まれ避けられるも、弱き赤子は守られて育てられる。
誰もが、前向きが意欲的姿勢と称えられる。しかし、後ろ向きでも、誰も見えていないものを見付けるかもしれない。
誰もが、交遊し友誼を深めることはイイことだと思わない者はない。
だが、現代の先端の通信機器で情報と交信が飛び交うこの異常な現状に、誰もが内心おかしいと思いつつ、それを手離せない。
静かに、徐に、ゆったりと自己を見詰める時間を奪われている今、それが本当に幸せな事か、豊かな事か、老子なら我々に問い詰めるだろう。
情報が多いということは、真の知識が少ないということだ。交遊が広いということは、真の絆が弱いということだ。
味が濃いということは、薄い味の本来を知らないということだ。

多忙とは、多くの心を亡うと書く。何か気忙しい毎日に、自分を亡なっている現代人に警鐘を鳴らしている。
そして、男性本位の人類有史こそ、悲劇の歴史であった。国取り合戦の無い無史の時代にこそ、生命賛歌の女性本位の泰平が続いていた。
毎日が平和過ぎて、それが当たり前過ぎて、何も書く必要が無かったまでの事だ。まさに「無事」なのだ。
無事こそ、何も無い事こそ、慶賀なのだ、祝福なのだ。
男女の性を超えて生む女性こそ、天地のひな型であり、生命を生み出す聖なる器であった。女性や赤子の柔弱の徳こそ、最も堅牢で長生で、物事を解決する近道であった。
そのイノチの根源、「母性」に帰れと、老子は力説したのだ。
そして、創業へ

そんな時、故福岡正信翁の自然農法「無為にして化す」、耕さず、肥料もやらず、何も為さずして、農産物を生むことに瞠目した。無の観念を形にする、想いを物にする。
そんなことが可能なのかと狂喜した。この道を進もう、と希ったのだ。
それが、まほろば創業であった。

丁度その頃、世はバブル前夜。その後日本は景気の絶頂期に向かい、やがて衰退期に差し掛かかるのだった。
全く世に疎い私は、それさえ気が付かずに、最終的に自然食の道を選んだ。家内の長年のマクロビオテックと私の菜食主義が当然帰結する選択でもあった。
その頃、日本は戦後30~40年を経て、経済復興はしたものの、自然破壊、教育崩壊、人心荒廃……などなど、その綻びは至る所に現れ、それから30年は下り坂を転ぶように下降線を辿った。
まほろばも、創業35周年を迎えようとする時、表向きは自然食品であったが、裏の経済システムは、全くの資本主義、貨幣経済の枠取りの中、何ら一般企業と変わらないことに改めて気付くことになる。
会社という組織は、決して根本的な自然回帰に成り得ないことに愕然とするのだ。
ただ、それを持ち支えていたものは、誰にも頼らず、何処にも属さずという自立精神と0-1テストによる判断だったと思う。
大きな組織で自然食運動を始めた同志が、最後には次々と批判の対象であったはずの大企業資本家の軍門に下っていく姿に、理想が現実と一致する事の難しさを知ったのだ。
あの起業の精神と努力は、一体何だったのか。
「懐かしき未来」

3年前に開催されたまほろば30周年祭は、「懐かしき未来」というテーマだった。

この名付け親でもある環境活動家ヘレナ・ノーバーグ=ホッジが、チベット・ラダックに取材したのが35年前、そして原題「ANCIENT FUTUREエンシェント・フューチャーズ(古代的な未来)」を刊行したのが20年前。
自給自足の慎ましくも豊かな暮らし。伝統が息づく敬虔な日々。夢のような理想郷。突如、そこに襲い掛かった近代化と開発の嵐。
このグローバリゼーションは、忽ちのうちに貨幣経済で貧富の差をもたらし、不要な物への欲求を生み出し、掛け替えのなき時間と幸福を奪った。
美しくも小さき山間を忽ちにして攪乱破壊させ、素朴な村民を狂わせる資本経済の魔力の恐ろしさ。
ヘレナ女史は、その訴えと本源に帰る生き方を世界の心ある人々に発信した。
「未来に懐かしさを」、と。
時同じくして、1983年にまほろばが創業し、浄活水器「エリクサー」を開発して世に問うた1998年に、一文「小国寡民」を図らずも書いた。それが20年前であった。
「全ては小さくあるべし」、と。
そして、今、まほろばも岐路に立たされている。
単なる経済行為としての店であって良いのか。
再び、創業の精神に立ち帰らざるを得ない時に戻った。
再びと帰る

「ゆっくりと、そして着実に歩めば、このレースに勝つ」
果たして何に勝ったのだ。
私は再びと、13歳の春に戻っていた。
「Slow and steady wins the race」
そのスローとは何だったか。そのステディとは何だったか。そしてそのレースとは何だったか。
「決して大きくしてはいけない。拡げない」と自分にも課し、みんなにも伝えて来た。
それは、着実な歩みであった。辛抱強いゆっくりした足取り。伸ばせる伸び代、可能性はいくらでもあった。
しかし、あえて拡大の道を選ばなかった。そのお蔭か、薄紙を重ねるようにして着実に会社は伸びて、力を蓄えた。
だが、事ここに至って、漸く気付くのだ。
目指したものは、ここだったのか、と。人の健康、安心安全の物を送り届ける。それは、天から与えられたミッションとしては、この上ないものだった。
まさに誇れるものだった。だが、何かが違っていた。働く喜び、仕える喜び、伝える喜び。掛け替えのないものに違いない。だが、ここは都会。
自然の疑似体験でしかなかった。
そこに、人類が全生活から乖離して、仕事だけを分業する苦しみ、自然と分離する悲しみに思い至ったのだ。
効率的で蓄財的な生き方の破綻をそこに観たのだ。
生き方そのもの、在り方そのものの違いをアリアリと見せつけられた。
このままで良いのか。このまま続けるのが良いのか。
Slowとは、商売の行き方だったのか。
ゆっくりとは方法ではなく、生活の時間そのもののはずだ。
着実も、地べたに足を着けたライフスタイルだったはずだ。
我々人類は、遠く離れてしまった。
引き戻すには遥か彼方、引き返すには遅かったのか。
しかし、顧みよ、地は何十億年からも、同じく大地で、天空も何百億光年からの光が届いて変わりがない。
変化も大きく望むべきでない。足元の小さい処から。
足取りも早く取るべきではない。身のの幅でゆったりと。
まほろばも、ゆっくりゆっくりであるが、着実にを徐々に切り替えながら、母なる大地に着地させたい。
「母性」に生きる

太古は未来であり、未来は太古でなくてはならない。
過去も現在も未来も一切はイコールなのだ。
「懐かしさ」は、後ろ向きではなく、むしろ、前向きなエネルギーなのだ。それは、未来と過去を繋ぐ魔法の力なのだ。
思いっきり昔を慕い、思いっきり未来の平和を描く。それを感じ取る力こそ「情緒」なのだ。
「情緒」とは、「母性」を心の太陽とすることだ。
太陽がすべてを隈なく照らす如くに、全てのイノチと繋がる事なのだ。
「母」こそ、みんなの太陽で、情緒で、懐かしさなのだ。
「まほろば」は、もう一度生まれ変わって、太陽のように親しまれ、慕われ、愛される店でありたい。
老子は、白髪の翁でなく、今生まれたての「赤子」であった。
宮下周平著『続倭詩』Amazon書評 より引用
・一読してまず、著者宮下周平氏のその碩学ぶりに驚く。この本を彩る話題も時代も人物たちも多岐多彩。
話題は、日本に四季ができるわけから秦の始皇帝、日本古代史の謎の人物徐福、孔子の作曲とされる曲や諸葛孔明が奏でた古琴、龍安寺の石庭を黄金律で鑑賞する視点、民謡江差追分、タイやラオスの村人たちとのフェアートレードから生まれた布、味噌・醤油・日本酒の個々の蔵元から発酵食品全般、身近な生活の一つ一つのシーンまで。時代は紀元前3世紀から、江戸、明治、昭和、現在の福島と網羅。
登場する人物は上記の中国人徐福から、鴨長明、明治期に来日した多くの外国人たち、昭和の名僧たち、マルク・シャガールや上村松園などの画家、数学者の岡潔、発酵学の小泉武夫などなど国の内外・古今にわたっている。
この本に出てくるエピソードは、普通では到底考えられないような、邂逅や出会いに満ちている。
例えば、孔子の76代目の孫と徐福72代目の孫と著者との出会いだ。
巡り会いが生み出す驚くような実りにも溢れている。著者の願いに響振するかのごとく世界中から集まってくる原料や材料で出来上がっていく新しい品々の例。
人生はなんて豊かなのだろう。
「求めよ。さらば与えられん。」
読者はこの本を読みながらこうした夢もみられるのだ。
採用した字体、使っている紙にも著者宮下周平氏のこだわりが行き渡っている。写真家島田浩さんの写真もすてきだ。
巻末に収められた、地球環境問題研究家の船瀬俊介さんと国際自然医学会会長の森下敬一さんと著者との鼎談も、生命の根本としての水に焦点をあてながら幅広い話題におよび、多くの示唆を与えてくれる。
名著の定義が「読むたびに発見があること」だとすれば、この本はまさしく名著と言える。読むたびに新しいことに気づかされ、新たな知的探求が促される。著者と読者の感応道交を味わえる一作だ。
【前回のコラム】

宮下周平
1950年、北海道恵庭市生まれ。札幌南高校卒業後、各地に師を訪ね、求道遍歴を続ける。1983年、札幌に自然食品の店「まほろば」を創業。
自然食品店「まほろば」WEBサイト:http://www.mahoroba-jp.net/
無農薬野菜を栽培する自然農園を持ち、セラミック工房を設け、オーガニックカフェとパンエ房も併設。
世界の権威を驚愕させた浄水器「エリクサー」を開発し、その水から世界初の微生物由来の新凝乳酵素を発見。
産学官共同研究により国際特許を取得する。0-1テストを使って多方面にわたる独自の商品開発を続ける。
現在、余市郡仁木町に居を移し、営農に励む毎日。







