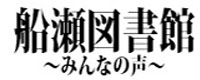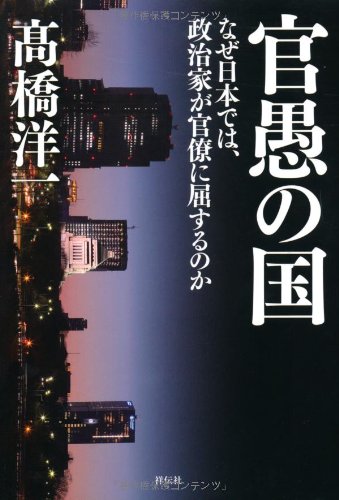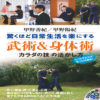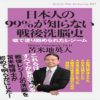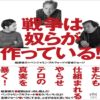「試験に通ったエリート」に弱い日本人
本書の解のひとつを先に記しておく。それは「日本の官僚は無能である」ということだ。
正確を期すなら、日本の官僚は「ごく一部を除き」「本来の優秀性とは別の意味で」無能である、と表現してもいい。
霞が関はほとんど無能の集合体である。のっけから、あえてそう断言しよう。
ただし世間一般の目から見れば、日本の官僚は優秀ということになっている。その一般の尺度を差し置いて、私が彼ら(かつては私自身もその集団の中にいた)を無能と断じる理由を、これから述べてゆく。
官僚には「エリート」という言葉がついて回る。
「エリート」は「選良」と訳されるが不思議なことに「選良」のほうは、選挙の洗礼を受けたという意味で政治家を指すこが、とが多い。

それはともかく、政治家とともに「政治エリート」群を構成する官僚は、庶民との比較において優秀とされてきた。なぜか。理由は単純である。官僚は難しい試験に通っている。
日本人は「試験に通っている」という事実の前に圧倒的に弱い。それだけでであの人は立派だ」と認定する癖がある。
学歴社会を生きる日本人は、誰しも何回かスクリーニング(ふるい分け)の洗礼を受けている。
中学・高校・大学受験。あるいは就職のための入社試験。
そして、そこでふるい落とされた経験があるはずだ。不合格の結果を「俺はあのときの試験に受からなかった」と受け入れ、反面、合格者に対しては「俺が落ちた試験に受かった」と認めざるを得ない。
そこにはある種の納得感がある。
だから競争倍率や難易度が高いとされる試験であればあるほど、合格した人間を優秀だと思う。
もちろん、試験に通りさえすれば高級官僚になれるということは、人間の出自に無関係という意味で平等であるし、官僚をグレードアップするひとつの仕組みではある。
一定のスクリーニングを経て「立派な選良」が誕生すること自体に嘘はない。
ちなみに私自身、大した家柄の出ではないけれど、「試験に受かれば官僚になれる」仕組みの恩恵に与った一人である。
ただし、この平等性は、矛盾するようだが恐ろしいまでの差別性と表裏一体でもある。
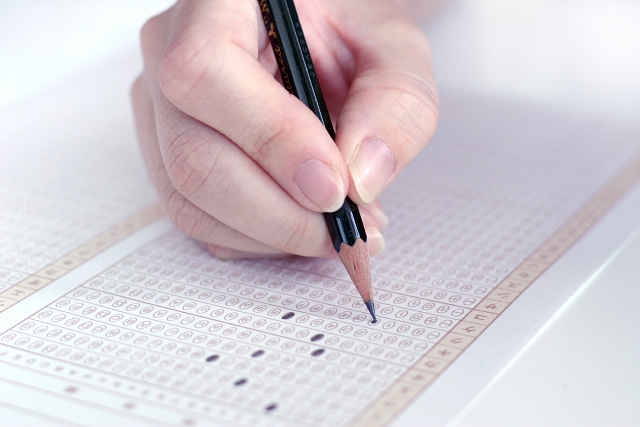
なにしろ試験に受かれば22、23歳で将来が保障されるのだ。
「官僚」の肩書を手に入れた時点で老後の心配が消える。定年を迎えても天下り先が待っていてくれる。
民間と決定的に違う点である。
今の日本社会で人間の一生を保障するような制度はあり得ないわけで、試験の合格をもって確実に安泰な人生がもたらされる官僚制は、
現代唯一の身分制度と言って差し支えないだろう。官僚と非官僚=民間との間には、見えざる差別が存在するのだ。
天才は、いらない
官僚は易しい問題を解く能力に長けている。
裏返せば、難しいことには手を出さない。答えが分かっていることを簡単に処理する。
その意味での優秀さであって、試験によって選別されたにすぎない。官僚の能力とは、しょせんその程度のものなのである。
平たく言うと、官僚には秀オは必要だが、天才はいらない。
天才的な人物は、ときに常人とは思えないような行動をとったりするが、常人にはなしえない発想で新たな価値を創造する。
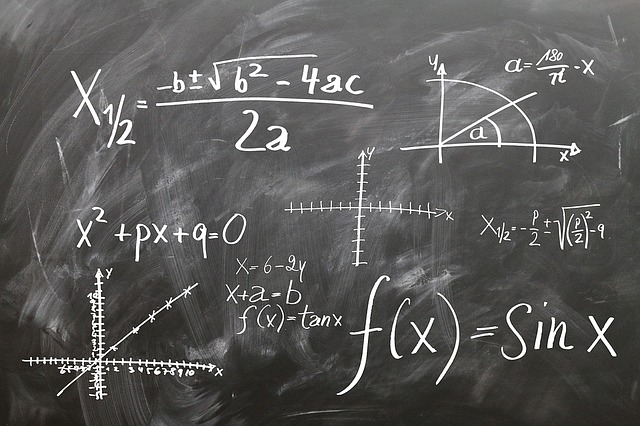
そのために、何かひとつのことに執着しつづけたりもする。だから天才なのである。
行政の世界では、新しい問題について対応することはあり得ない。
すべて定型的な問題である。官僚には定型的な問題への対処能力だけが求められ、それ以外のことはまった<する必要がない。いや、対処できない。
したがって官僚に「未曾有の問題」についての解決策を求めても、求めるほうが間違っている。
冒頭で私は「日本の官僚は無能である」と述べたが、国民が官僚に多くのことを求めたとき、その無能さは露呈する。
逆に「役人は判を押すだけの人間だ」と思えば、きわめて有能ということになる。
たしかに、あらゆる許認可事項において、判をしかるべき場所にきちんと押せるという意味では有能と言えるかもしれない。
だが、それは決して優秀であることにはならない。単に「特殊な能力」を有しているにすぎないのだ。
たとえば、日本人は戦後の高度成長を官僚が支えたと思っている。
つねに批判の矢面に立たされる官僚だが、それでも1960年代の繁栄をもたらした政策は官僚の力に負うところが大きいと、なおも評価が残る。
しかし、その評価は大きな誤解の産物だ。
私から見れば、日本の官僚はほとんど何もやっていない。
新しい価値を生み出していないからである。私が言う「無能」の論拠はここにある。
ところが日本人は官僚の「特殊な能力」を理解せず、盲目的に彼らを優秀だと信じ込んできた。よく言われる「官僚の野町性」、すなわち「お上がやることは正しい。
お上は優れている」という「官僚神話」が、いつの間にか醸成された。
その神話は国民の側がつくり上げたものであり、ほとんど幻想だと私は思う。
| 官愚の国 |
||||
|