小澤博樹 連載コラム
現代医学は日進月歩の勢いで高度に発展し続けているといわれている。しかしそれとは裏腹に癌による死亡率は年々高くなっている。
1970年代、癌により5人に1人が死亡していたが、1990年代には3人に1人が死亡している。そして現在もその死亡率は高くなってきている。
この事実は、癌に対する現代医学的治療が全く効を奏していないことをものがたっている。
癌を発症し、生命力の衰えた病人に対し、猛毒である抗癌剤を投与すれば病状はさらに悪化することは火を見るよりも明らかである。
火に油を注ぐとはまさにこのことだ。
癌治療において、今だに毒性の強い抗癌剤が使われる理由は、医療産業の利益をあげるために他ならない。病気の治療や健康を目的としたものではない。
このことを承知している医師たちは、自分が癌に罹患したとしても抗癌剤を自分自身に投与するようなことは決してしない。
抗癌剤を投与すれば、その副作用に苦しみ、免疫機能を破壊するため、結果的に癌による死期を早めることは分かっているからだ。
高額な医療費を支払ってまで自分の命を削ることなどできるわけがない。それでも抗癌剤を自分自身の体に投与するという医師がいるとすれば、それは全くの無知か、馬鹿としか言いようがない。
癌や白血病に対して用いられる抗癌剤は、その強烈な酸化作用によって癌細胞を溶かし、いかにも癌病巣を縮小させ、一見、癌を治癒させるかのような効果を示す。
しかし抗癌剤のもつ酸化作用は、癌細胞のみならず、癌細胞以外の全身の細胞にも作用するため、かえって他の臓器や組織からも発癌しやすい状況をつくりだす結果となる。
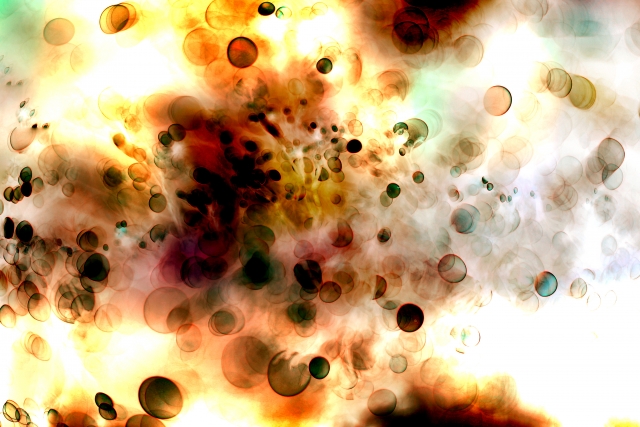
抗癌剤
つまり抗癌剤イコール発癌剤であり増癌剤なのである。
そして、それにより、癌の再発や転移をおこしやすくするのだ。
抗癌剤が毒物であることは、医学部の薬理学の教科書にもはっきりと明示されている。
抗癌剤の癌に対する薬理作用や作用機序を説明すると次のようになる。
1 アルキル化薬
ナイトロジェンマスタードN・オキサイド(ナイトロミン)やサイクロフォスファマイド(エンドキサン)などがある。
ナイトロジェンマスタードは第一次世界大戦に毒ガスとして用いられたイペリット(マスタードガス)をもとにしてつくられた抗癌剤である。
アルキル化とは、化学的置換反応または付加反応によって、癌細胞を構成する分子結合を別の分子結合に置き換える作用のことで、これにより癌細胞のもつ本来の機能つまり細胞酵素、核酸代謝機能を阻害する。
その結果癌細胞のDNA合成も阻害し、癌細胞は死滅する。しかしこの阻害作用は、癌細胞以外の細胞にも作用するため、多くの副作用が出現する。
嘔吐、脱毛の他、白血球減少、血小板減少などの骨髄機能抑制症状をきたすのである。
2 代謝拮抗物質
癌細胞の発育や増殖を抑制する作用がある。この代謝拮坑作用も、癌細胞以外の細胞にも働くために副作用を発生させる。
癌細胞のDNAを合成するために必要なプリン体やピリミジン、葉酸、グルタミンなどを別の物質に置きかえることによりDNAの合成を阻害する抗癌剤である。
プリン代謝拮抗物質として6MP、ピリミジン代謝拮抗物質として5・FU、葉酸拮抗物質としてメソトレキセートなどの抗癌剤がある。
3 植物アルカロイド
植物のもつ毒素を抽出したものと石油化学により合成したものとがあり、ヴィンクリスチン、ヴィンプラスチンなどの抗癌剤がある。
癌細胞の有糸分裂を抑制する作用があるが、これも癌細胞以外の細胞にも同様な作用をしめす。
4 抗癌剤として用いられる抗生物質(抗腫瘍性抗生物質)
細菌の代謝産物から得られるある種の抗生物質には、癌細胞内の核酸合成阻害作用があるため、その成分を科学的に合成し抗癌剤として用いている。
アクチノマイシンDやクロモマイシンはRNA合成阻害剤として、マイトマイシンCやブレオマイシンはDNAの合成阻害剤として働く。
副作用として嘔吐、造血機能抑制、白血球や血小板減少、下痢、脱毛などがある。
抗癌剤のもつ発癌性について、世界保健機関WHOの下部組織である国際癌研究機関(IARC)が1969年から研究を進めており、1991年にその結果を論文にまとめている。
約50種の抗癌剤について、動物実験や疫学調査がなされ、抗癌剤のもつ発癌性を5段階(グループ1・2A・2B・3・4)に分けて評価している。
グループ1は人に対する発癌性が明らかに認められる抗癌剤。
このグループにはクロラムブシル、サイクロフォスファマイド(エンドキサン)などがある。
グループ2Aは人に対する発癌性が多分にあると考えられる抗癌剤。これには、ナイトロジェンマスタード、シスプラチン、アドリアマイシンなどがあげられる。
グループ2Bは人に対する発癌性の可能性がある抗癌剤。これはマイトマイシン(MMC)、ブレオマイシンなどがあげられる。
グループ3は人に対する発癌性についてまた評価できていない抗癌剤。
これはフルオラウラシル(5・FU)、メソトレキセート、アクチノマイシンDなどがある。
グループ4は人に対する発癌性がないと判断される抗癌剤。これに相当する抗癌剤は存在しない。
つまりすべての抗癌剤には程度の差こそあれ発癌性があるという評価がなされている。
最も発癌性リスクの高い抗癌剤として、アルキル化薬があげられている。サイクロファマイドが膀胱癌を、メルファランが急性白血病をおこすことが確認されている。(表1)
表1 抗癌剤と関連が指摘されている二次癌
|
抗 癌 剤 |
二 次 癌 |
|
メルファラン |
急性白血病 |
|
シクロフォスファミド=サイクロフォスファマイド |
膀胱癌、悪性リンパ腫、急性白血病 |
|
ブスルファン |
急性白血病 |
|
クロラムブシル |
急性白血病 |
|
チオテパ |
急性白血病 |
|
ロムスチン アザチオプリン *MOPP |
急性白血病 急性リンパ腫、皮膚癌 急性白血病 |
Marselos M・Vanio H・Carcinogenic properties of pharmaceutical agents evaluated in the IARC Monographs programme.
Carcinogenesis 12:1751-66,1991.より抜粋して作成「メディカル朝日」1993-3
*MOPP:4種の抗癌剤を併用したもの
抗癌剤投与による発癌の原因としては、抗癌剤自体がもつ発癌性、抗癌剤のもつ免疫抑制作用、抗癌剤が他の抗癌剤のもつ発癌性、抗癌剤のもつ発癌作用を助長することなどがあげられる。
大阪大学医学部第二外科の藤本二郎講師らの調査でも、MMCと5・FUなどの抗癌剤をそれぞれ単独投与した場合の抗癌剤による発癌率はそれぞれ5.8%と4.8%であったのに対し、両者を併用した場合では10.1%という高い値を示した。
つまり発癌性が低いとされる抗癌剤も、併用によって発癌性が増強される可能性がある。
さらに藤本講師らは、抗癌剤にクレスチン・ピシバニール及びレバミゾールという免疫賦活剤を併用した「免疫化学療法」をした胃癌患者についても調査をおこなっている。
その結果、手術だけ行った症例では、術後5年以後で5.6%、抗癌剤(MMCと5FUまたはテガフール併用)投与例では13.6%、免疫化学療法施行例では20.5%の発癌率を示している。
つまり、免疫療法と抗癌剤を併用した症例の方が発癌率は高かったのである。現代医学で使われる抗癌剤はもちろん、免疫賦活剤も人体にとって有害であることが分かる。
現代医学で使用される免疫賦活剤はその名とは反対に免疫機能を向上させてはいないからだ。他の化学薬品となんら変わりはない。
アルキル化薬抗癌剤を主体としたMOPP療法(複数の抗癌剤を投与するもの)がホジキン病(悪性リンパ腫)に対して1964年から行われているが、その後10年たった1970年代後半から1980年代にかけて急性白血病が増加していることが報告されている。
その発病の確率は一般の白血病の発病の100倍以上も達している。
抗癌剤により一個の癌細胞を殺すことができたとしても、同時に千個の健常細胞も殺される。この現象は抗癌剤のもつ薬理効果からみても充分うなずけるものである。
このように抗癌剤のもつ毒性は、癌細胞だけでなく、癌細胞以外の細胞にも作用するために、毛髪が抜け落ち、貧血や出血、食欲不振脱力感など多くの副作用(実は主作用なのだが)を発現させる。
そして抗癌剤投与により免疫機能や諸臓器の機能をも障害し、人間の生命力を奪い取るのである。
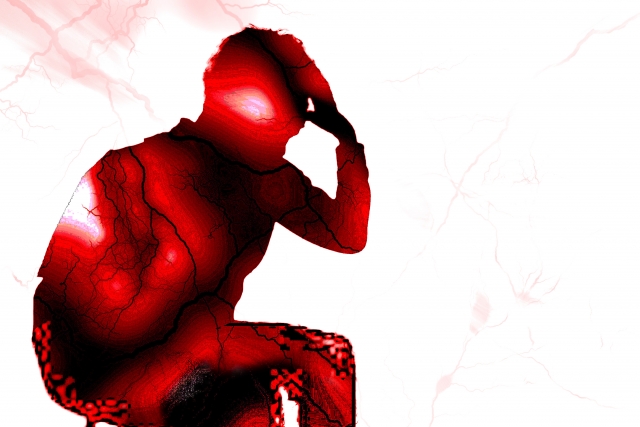
それにもかかわらず、現代医学は毒物そのものである抗癌剤を正規の治療薬としていまだに用いている。これは殺人行為にも匹敵する愚行である。
現代医学が用いる他の薬剤や手法と同様、抗癌剤も癌治療に役立つどころか人の寿命を縮めるものでありながら、国はこれを治療薬として認めている。
抗癌剤を国が認定する場合、動物実験で動物の癌が4週間持続して縮小していれば、抗癌剤として認定される。
その後、抗癌剤投与をつづけていき、癌がまた大きくなったとしても認定を取り消されることはない。
たった4週間の癌縮小効果があればよいという認定基準にもおどろかされるが、裏をかえせば、抗癌剤は4週間しか効力がないということを物語っている。
そして4週間ほど抗癌剤を投与していくと、細菌が抗生物質に耐性能力を獲得いていくのと同様に、人間の癌細胞も抗癌剤に耐性能力ができ、その後は、癌増殖のスピードが増し、転移や拡大をおこしやすくしていくのである。
抗癌剤という毒物を人間に投与すれば、その毒性が血液や血球を汚染し、汚染された赤血球が癌細胞に変化し癌を増殖させることになる。(千島学説)
アメリカにおける癌研究の権威である米国立癌研究所(NCI=NationalCaner Institute)のデヴィタ(Vincent T.DeVita,Jr.)所長は、1985年、抗癌剤を癌患者に投与することによって、癌細胞のもつ反抗癌剤遺伝子(ADG=Anti-Drug Gene)の働きで抗癌剤に耐性を示すとの見解を米国議会で証言している。
また同じくNCIは1988年、「癌の病因学」という数千ページにもわたるレポートを作製し、その中で抗癌剤は、これを癌患者に投与することによって癌をかえって増殖させてしまう増癌剤であると報告している。
これは抗癌剤を投与された、15万人の癌患者の疫学的調査を行なったところ判明したもので、肺癌や乳癌、卵巣癌、ホジキン病などの患者に抗癌剤を投与すると膀胱癌を併発し、白血病では肺癌、卵巣癌では大腸癌を併発する傾向が高いと述べられている。
くり返しになるが、抗癌剤の人体への投与によって、癌細胞のみならず他の細胞までも破壊してしまうこと、それによって、諸臓器の機能や免疫機能も破壊してしまう毒性の強いものである。
これで癌は治るはずもなくかえって癌を増殖させてしまうのは当然のなりゆきである。
医学分野の各専門家から抗癌剤が否定されてきているにもかかわらずいまだ日本の医学界では抗癌剤を癌患者に投与し続けている。
医療産業のみは莫大な利益を得られるが、患者側は何の利益もなく、さらにその寿命が削られているのが現状だ。
【参考文献】
「薬理学」 伊藤 宏・著 英光堂
「抗ガン剤で殺される」 船瀬 俊介・著 花伝社
「メディカル朝日1993-3」 朝日新聞社
「治す医者か、ごまかす医者か」 小澤 博樹・著 三五館
【こちらもオススメ】
現代医学における癌の三大療法(手術療法、化学療法、放射線療法)も有害無益

小澤 博樹
1949年愛知県碧南市生まれ。1974年東邦大学医学部を卒業後、同付属病院にて消化器外科学、一般外科学を専攻。
1984年、碧南市にて小澤医院を開業し、「食養生」を基本とした代替医療を展開し、現在に至る。
現代医学そのものが金儲け主義であると批判。自らは最少の費用で最大の成果を提供しようと模索する。頑固と良心の共存した、清貧な医者である。
マクロビオテック(玄米菜食)による体質改善、免疫力・自然治癒力の向上を図り、病気を治療に導く有床診療所「小澤医院」のHPはこちら→小澤医院
主な著書に「治す医者か、ごまかす医者か―絶対あきらめない患者学」「医者ができること、してはいけないこと―食い改める最善医療
」などがある。







