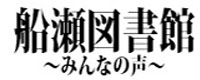磯貝昌寛の正食医学【第108回】心の陰陽
執着心を俯瞰する

幼子と積み木で遊んでいると、子どもは線路や家、お山やビルディングなど、色々な面白いものを作ります。
しかし、作ったと思ったら、ほんの少しの間でバラバラと壊してしまいます。
そして、また同じものを作ったり、違うものを作ったり、作っては壊し、作っては壊し、繰り返し積み木で遊んでいます。
私は作り上げたものを壊すのは何とも名残惜しくなります。
名残惜しいというよりも壊せない。それが子どもは何度でも壊しては作り、壊しては作りを繰り返す。
一度作ったモノへの執着など、まったくないかのようです。
私はこの幼子の執着心のないことに、妙に感心させられました。
子どもを観察しながら自らの執着心の有りようを、まざまざと考えさせられたのです。
ある雨の日のことです。私は傘を差しながら道を歩いていました。
自転車の傘さし運転が危険な行為なのは誰の目にも明らかなのですが、東京ではちょっとした小雨程度であれば多くの人がしています。
それなりのスピードを出した傘さし運転の自転車が2台、すれ違おうとした時です。
衝突したわけではないのですが、ハンドルの辺りがぶつかって両方の自転車がふらふらと倒れてしまいました。
倒れた2台の自転車に駆け寄って助けの手を差し伸べたのですが、どちらの人も傘を離さずに持っているのです。
ぶつかりそうになった時、とっさに傘を手放せば倒れずに済んだのに…。
人はなかなかこれができないのです。
病気の原因になっているものは一体何か、と考えることは少なくありませんが、多くの病気の人を診ているとあることに気づきます。
もちろんコレが全てというわけではありません。
ひとつの大きな要因として、それが「執着心」ではないかと感じるのです。
執着心は時に嫉妬心や猜疑心にも転化しますから、タチが悪いといえばその通りです。
執着という心は体の中の毒素から発せられているように思います。
執着心や嫉妬心、猜疑心が出てくるようであれば、体の浄化も道半ばではないかと思うのです。
心からも自分の浄血・浄身度がわかるのではないでしょうか。
心を俯瞰して、天から自分の心を観てみれば、体の中のことがよく見えます。
湧き起こってくる執着心や嫉妬心、猜疑心を押さえつけるのではなく、心を俯瞰して、食や生活から精進することが大切だと、多くの人を見ていても自分の経験からもそう感じます。
子どもに執着心がない、ということは、子どもは心身ともにきれいだと思うのです。
近頃は台風、地震、火山噴火と天災の連鎖です。前の天災を忘れる前に次の天災が起こりますから、激動の時代も本格化してきました。
自然災害は自然の中に暮らす私達には避けて通れない道です。
自然を俯瞰してみると、自然もまた、幼子と同じように、執着心がないように思います。
自然は「自ずから然る」という言葉の通り、「あるがまま」の状態です。
ディズニー映画「アナと雪の女王」の「♪ありのままの自分になるの」という歌詞は、「自分の中の自然性を取り戻したい」といっているのと同じではないでしょうか。
今の日本は経済再生を謳い文句に経済成長を掲げています。悪いことではありません。
しかし、生命力を貶める経済成長は根本的にありえません。本来の経済は人々の生活そのものです。
経済成長は生命力向上の先にあるものだと、自然は天災という形で私たちに教えているのだと、早くに気づく必要があるのではないでしょうか。
欲を俯瞰する
陰陽で見ると、執着心と粘り強さは一見すると同じ陽性のようでありながら、何かまったく異質なような気がします。
私の経験からも、粘り強い忍耐力は執着心があったのでは決して生まれてこないと感じるのです。
その現象だけ見ると、「執着」と「粘り」は共に強い陽性を持っています。
しかし、その根本はまったく異なるのではないでしょうか。
執着心は必要のないものまで何でも持ちたがります。持ちたがり屋とも知りたがり屋ともいえます。
一方の忍耐力は必要のあることにのみ、集中力を発揮します。
それより何より、忍耐力のある人は潔く、清々しい感じを周りの人へ与えます。
ところが執着心のある人はその物欲の強さから、周りの人々の気分を損ねる。
体の内側がきれいになってくると周りの人たちへ清々しい気を振りまきます。
周りの人が自然と元気になってくるのは、陰陽を孕んだ中庸の人間だからではないかと思うのです。桜沢如一は「忍耐は永遠なり」といったようです。
忍耐は中心に陽を持って、周りに陰を抱くと考えるのです。
万物、中心が陽であり、外側が陰です。忍耐は物の真理をあらわしたひとつのカタチといえるのではないでしょうか。
執着心の陰陽はその逆です。自分の芯に軸がないので、周りのものをどんどん掴もうとしてしまうのではないでしょうか。
正しい食生活の実践は、周りの人々へよい気を与えると思うのです。
赤子の笑顔が何ともいえない幸福感を人に与えるように。とはいえ、偏った人生から中庸な人間になるには時間がかかります。
ですから、これを人に求めてはいけないと思うのです。中庸さは自分に求めるものであって、人に求めるものではないようです。
「病気は健康への導き」と同じように、執着心や排他心、嫉妬心は心を中庸へ導く働きがあります。
心のアカを糧に日々の生活を見直すことができたなら、なんと素晴らしい人生を送ることができるでしょうか。
人間は生きている限り、なんらかの形で執着心を持っています。
執着心は物欲のひとつのアラワレでもあります。執着心を消したい、なくしたい、と思っても、そう簡単に消えてなくなるものではありません。
師の大森英桜は「無欲とは欲が無いのではない、無限を求める欲をいう」と生前に語りました。
執着心も他の物欲も、消そうとするのではなく、乗り越えて新しい世界に羽ばたいていくことが大切ではないかと思うのです。
「人間は欲求の束である」と云ったのは、教育家で実践哲学家の和田重正です。
和田氏は欲求を突き詰めると、欲求を消し去りたいという無欲欲なるものが出てくるから、人間はどこまで行っても欲の束である、と云いました。
大森も和田氏も人間観察から自己を俯瞰し、自然と宇宙を見つめたら、同じような境地に至ったのでしょう。
心は身体そのものです。心身一如と云うように心と身体は別々のものではなく一体です。
執着心も他の物欲も、日々の簡素な生活で害のないものへと変化していきます。むしろ、強い執着心や物欲のお蔭でマクロビオティックの生活に有難さを感じて実践できるわけですから、執着心と物欲ほど有難いものはないと感じるのです。
月刊マクロビオティック 2020年12月号より
【こちらもオススメ】
現代人の多くの肝臓が悲鳴を上げている【肝臓の疲れには野菜の排毒食】
マクロビオティックとその料理法に関するホットな情報、健康と美を創り、生命をはぐくむための食と、その知識のご紹介、などなど・・・。
あなたの人生を豊かにする情報が毎号満載です。
サイトの方はこちらから: マクロビオティック日本CI協会
磯貝 昌寛(いそがい まさひろ)
1976年群馬県生まれ。
15歳で桜沢如一「永遠の少年」「宇宙の秩序」を読み、陰陽の物差しで生きることを決意。大学在学中から大森英桜の助手を務め、石田英湾に師事。
食養相談と食養講義に活躍。
「マクロビオティック和道」主宰、「穀菜食の店こくさいや」代表。