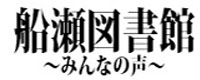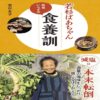今月のFACE 生産者紹介 たきかわナタネ生産組合(北海道滝川市)

●消えゆく日本の菜の花畑
菜種はかつて日本各地の農村で栽培され、地元の搾油屋さんで炒って搾って菜種油となり、家庭の調理油として広く庶民に使われてきました。
国産菜種の年間生産量は昭和30年代に約30万トンのピークを迎え、自給率は100%でした。
しかし1961年の大豆貿易自由化(油糧大豆輸入)、1971年に菜種輸入自由化で価格競争に負け、国内の菜種の作付け面積は急減。
さらに、カナダを主生産地とするキャノーラ種は当時すでに低エルシン酸に品種改良されていましたが、日本在来種の菜種はエルシン酸含有量が多く、食用油として大量摂取すると心臓への負担が発生すると指摘されたことも逆風となりました。
近年の国産菜種の年間生産量は2千トン未満。
自給率は0.04%に過ぎず、ほぼ全量をカナダやオーストラリアからの輸入に頼っているのが現状です。
●日本一の菜種の町たきかわ
そんな中、地域ぐるみで菜種栽培に取り組み、栽培面積を増やしてきた町があります。北海道のほぼ中央部、石狩川と空知川に挟まれた平野部にある滝川市です。

滝川で菜種栽培が復活したきっかけは、1990年に東北農業試験場で開発された低エルシン酸の国産品種「キザキノナタネ」です。
積雪寒冷地でも越冬でき、収量も優れていたことから1992年、北海道の優良品種に認定されました。
たきかわナタネ生産組合の宮井誠一組合長(73才)は当時、こう説いて回りました。
「研究者が苦労して開発したこの菜種を、我々は頑張って作らねばならん。そうすれば心ある消費者が必ず現れる」。
1999年頃から次第に栽培面積が増え、2000年にナタネ生産組合が発足。2010年の菜種作付面積は187ha、単一市町村としては日本一です。
現在、58名のメンバーが畑作の輪作作物として菜種を栽培しています。宮井さんは小麦→菜種→小麦→大豆→ビート→小麦→という作付け。
「菜種のあとの小麦はよく育ちます。油分豊富な茎葉を鋤き込むからでしょう」。

8月下旬~9月上旬に種をまき、1週間ほどで出芽。
冬の間は雪の下で越冬し、3月下旬から4月上旬の雪解け後に再び生長を始め、5月に黄色い菜の花を咲かせ、7月下旬頃から収穫します。
組合では栽培技術を学び合うほか、菜種の花が咲き揃う晩春には毎年「菜の花まつり」を開催。
2011年2月、北海道開発局が地域活性化に貢献する活動をたたえる「わが村は美しく・北海道」運動第5回コンクールで、たきかわナタネ生産組合は景観部門で特別賞、地域特産部門で銅賞を受賞しました。
●日本初の国産菜種サラダ油、誕生
2010年夏、滝川町の菜種生産者と、圧搾製油メーカー平田産業(福岡県朝倉市)、国産菜種油を拡販するムソーがともに手を取り、滝川産菜種100%の「国産なたね油」が発売されました。
さらにこのたびムソーから発売する「国産なたねサラダ油」は、財団法人 日本油脂検査協会
(2011年4月1日より公益財団法人 日本油脂検査協会に名称変更)のJASに指定された認定工場から生まれた日本初の国産菜種使用の菜種サラダ油です(※)。
まず菜種を蒸して焙煎し、機械の圧力をかけるだけの圧搾一番搾りで搾油します。

搾った原油に酸を加えてガム質などの不純物を沈殿させ、次に約70℃のお湯で8~10回湯洗いをし、水と油が分離する力を利用して不純物を取り除いたのが「国産なたね油」です。

「国産なたねサラダ油」はこの後、白土と活性炭で脱色し、高温高真空状態で水蒸気を加えて脱臭します。
ムソーは今後、国産なたねサラダ油を使ったマヨネーズやドレッシングなどの開発も進めます。
育てる人・搾る人・運ぶ人がスクラムを組んだ取り組みが、日本の農業を元気づけ、自給率アップの一助になればと願っています。
※サラダ油は日本農林規格(JAS)により規格が定められています。JAS認定工場で製造され、品質検査を受けて合格したものでなければ「サラダ油」を名乗ることはできません。
10600(ムソー)国産なたねサラダ油 450g
972円(税込価格)900円(本体価格)
原材料:食用なたね油
ここがGOOD!
●北海道滝川産「キザキノナタネ」100%
●溶剤を使わない、昔ながらの圧搾法一番搾り
●安全な物理的精製で、淡白で軽い風味を実現
自給率わずか0.04%の希少な国産菜種の中でも、たきかわナタネ生産組合(北海道滝川市)の菜種を限定使用。
品種は国内で開発された低エルシン酸品種「キザキノナタネ」です。滝川産のキザキノナタネはオレイン酸たっぷり。
もちろん遺伝子組み換えの心配はありません。
この産地限定の菜種を圧搾法で搾った一番搾りのみを使用。
油の不純物を酸による前処理と丁寧な湯洗いで取り除き、白土と活性炭で脱色、高温高真空状態で水蒸気を加えて脱臭。
使い勝手のいいサラダ油に仕上げました。
※従来の日本在来種の菜種はエルシン酸含有量が多く、食用油として大量摂取すると心臓への負担が発生すると指摘されていました。
東北農業試験場が開発したキザキノナタネはエルシン酸をほとんど含まない、高品質の国産品種です。
【こちらもオススメ】
奈良県産有機栽培の梅を100%使用し伝統製法で仕上げた梅干し
月刊「むすび」 2011年04月号より
正食協会では、月刊誌「むすび」を毎月発行しています。「むすび」は通巻600号を超える息の長い雑誌です。
マクロビオティックの料理レシピや陰陽理論、食生活、子育てや健康、環境問題など幅広いテーマを取り上げています。
ぜひ、あなたも「むすび」誌を手にとってご覧になってみませんか?
サイトの方はこちらから: 正食協会