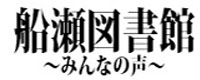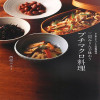森下敬一 『食べもの健康法』●しょうゆ
日本的な味のパターンのもとになっているのは、しょうゆである。
日本人にとっては、一日として欠かすことのできない調味料だ。
外国に住む日本人では、材料は何であれ、しょうゆで煮つけたり、しょうゆをつけて食べたりすることで、日本料理への切ない郷愁をなんとかなだめられる、ということだ。
この日本食を代表する味が、いまや世界の味になろうとしている。

しょう油はソイソースと呼ばれ、人気急上昇中なのだ、とはいえ、しょうゆが海外流出するのはいまにはじまったことではない。
フランスのルイ14世 (1638~1751年)は、宮廷料理の花といって珍重した、という記録もある。
しょう油の本質は、塩分18%を含む塩味料である。
けれど発酵・熟成によって、その塩分はすっかりカドが取れた刺激性の少ないものとなっている上に、実に多彩な有効成分が含まれているのである。
まず、うま味成分としてグルタミン酸、アルギニン、リジンなどの各種アミノ酸が含まれる。
原料である大豆、小麦からきたものだ。
わずかに酸味があるのは、発酵によって生じた乳酸が含まれるためで、これがしょうゆに独特の重みのある味をつけている。
しょうゆの味を引き締めているのは苦味成分で、食塩のなかのマグネシウム塩や、原料のタンパク質の分解産物であるペプチドなどによるものである。
それから、ブドウ糖、グリセリン、アミノ酸がまろやかな甘みを添えている。しょうゆ独特の色は、熟成中に生まれるソヤメラニン酸による。
香気成分がまた大変なもので、発酵によって生じたアルコール成分に加えて、コーヒー、パイナップル、バラ、アーモンドなどの香気成分までもが含まれる。
これらの複雑な成分が総合されて、しょうゆは、塩分補給という本来の目的のほかに、うま味・香りをつけ、生くささを消し、ダシの味を強め、素材の風味を引き立てる・・・・・・といった働きをする。
日本の風土が生んだこの最高級の調味料は、総体的に淡白な味の穀菜魚食をおいしく頂けるようにするための、大自然の恵みなのである。
だから、しょうゆに親しむことは、日本的な味覚を守り日本の伝統的食事パターンを持続することにつながっていく。
そうなれば、必然的に日本人の健康は守られるわけだ。
味覚の混乱・無国籍化は不自然食品をはんらんさせ、健康の失墜を招く。
ケチャップ、マヨネーズその他得体の知れないソース、ドレッシング類は極力避けて、しょうゆを活用するよう心がけたい。
もちろん昔ながらの方法で作った本物のしょうゆでなければ意味はない。脱脂大豆を用いたもの、アミノ酸で化学合成されたもの、合成保存料を加えたものなどは失格だ。
■ れんこんのしょうゆ漬け
(材料)
・れんこん・・・400g
・米酢・・・1/4カップ
・にんじん・・・5cm
・白ごま・・・大さじ2
・しょうが・・・1かけ
・みりん・・・大さじ3
・しょうゆ・・・1/2カップ
・ミネラル水・・・1/2カップ
(作り方)
①れんこんは暑さ5mmに切り、ざるの上で、米酢を加えた熱湯を通し、日陰干しにしておきます。
②にんじんは細い千切りにし、熱湯をかけてざるに上げ、水切りしておきます。
③白ごまは香ばしく炒って粗ずりし、しょうがは薄切りにします。
④鍋にしょうゆ、みりん、ミネラル水、しょうがを入れて煮立て、10%に詰まったら、そのまま冷まします。
⑤容器に材料を入れ、重石をして冷暗所に一晩起きます。
【こちらもオススメ】
どくだみはめざましい解毒作用を持っていて体質改善に大いに役立つ
◆森下自然医学メールマガジン(無料)
好評発信中! 森下自然医学メールマガジン
無料登録はこちら: https://ws.formzu.net/fgen/S64007955/
『新医学研究会』のオリジナル物販: http://www.new-medicine.jp/sale/

森下敬一 (もりした けいいち) 医学博士
お茶の水クリニック 院長 千島・森下学説『腸管造血』提唱者
東京医科大学卒業後、生理学教室に入り、血液生理学を専攻。千葉大学医学部より学位授与。
新しい血液性理学を土台にした自然医学を提唱し、国際的評価を得ている。
独自の浄血理論と、玄米菜食療法で、慢性病やガンなどに苦しむ数多くの人々を根治させた実績をもつ自然医学の第一人者。
著書に「血液をきれいにして病気を防ぐ、治す 50歳からの食養生 」「ガンは食事で治す」など約80冊がある。